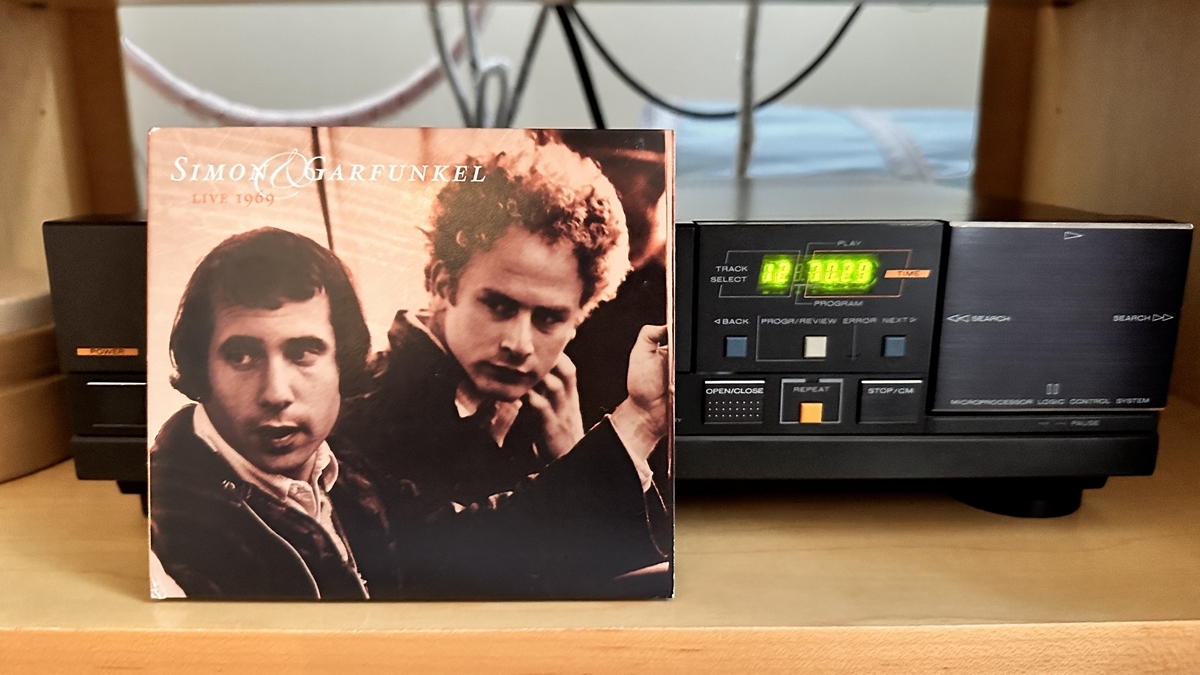最近、カケハシレコードで、1960年代〜70年代のスウェーデンのヒッピーグループ、「Harvester(International Harvesterから名前を縮めたもの)」の中古CDを購入して、聴きながらいろいろ思うことがあったのでその話を。
僕が最初に「International Harvester」のアルバムを買ったのは1990年ごろで、明大前にあった「モダーンミュージック」というサイケデリックアンダーグラウンド専門のお店でだった。インターネットがない時代なので、このアルバムを巡る言い伝えのような話がいろいろあったが、このCDのライナーを読んで、このグループが生まれた1960年代後半の様子がわかってきた。
共同体の音楽を目指したInternational Harvester
すべては、1967年の春に米国ミニマリズムの作曲家Terry Reillyが、ストックホルムの音楽大学に客演して、学生と一緒に「In C」と「Olson III」の2曲を演奏したことに始まる。音大生で当時の十二音技法やセリーによる現代音楽に行き詰まりを感じていたBo Anders Perssonは、「In C」の演奏に参加したことで大きく感化され、シンプルで共同体的な音楽を演るためにPärson Sound を結成し、それがよりコミューン的なInternational Harvesterに発展していく。
もう一つの動機には、これも当時の若者が抱いていた反資本主義、共産主義や社会主義への憧憬というイデオロギーもある。それは彼らが演奏の拠点が、共産主義者が集う「カフェ・マルクス」という場所だことからもわかる。当時のインタビュー映像がYouTubeに残っている。
司会者の「どうしてシリアスな(芸術的な権威のある)音楽を演奏しないのか?」という問いに「我々の音楽が最もシリアスであり、これまでのシリアスな音楽は現実や社会、コミュニティとの接点を完全に失ったエリートのものにしか過ぎず、大衆が理解できるものとかけ離れてしまった。」とこれを批判し、「どんな文化おいても誰もが音楽に参加することができ、演奏家と聴衆を分断することに意味はない」、「すべては政治的で、オーケストラも政治的なものとなっている」と指摘する。そしてカメラは彼らが演奏するサイケデリックな音楽に移っていく。
その音楽はInCの影響か、単純な繰り返しが多く、ハードであっても瞑想的で、メランコリックなメロディには、甘美的なところがあって親しみやすいもあり、まさしく「共同体としての音楽」としてある。その素朴で、無垢な憧憬が今でも聴き手に訴えかける力を失っていない理由かもしれない。

Harvester から Träd, Gräs & Stenarへ
「International Harvester」は、その後、「Harvester」へと名前を縮め、Bo Anders Perssonは、ストックホルムの電子音楽スタジオでの作品制作に戻り、その音源はbandcampにもあった。一部はWERGOからFolke Rabeの“WAS”とのカップリングでリリースされている。タイトルは「蛋白質帝国主義」というものだった。
「Love is Here to Stay」というタイトルの曲があるのが、「Harvester」の名残を感じさせる。
残りのメンバーは、「Harvester」としての音楽活動を続け、よりサイケデリックでドローンな音楽に傾倒していき、1970年代に入ると、「Träd, Gräs & Stenar(木と草と石)」にグループ名を変える。
終わりなきサイケデリックの旅
「Träd, Gräs & Stenar」としてのライブは、bandcampやYouTubeに多数残っていて、今でも活動が続いている。
bandcampにある1970年のライブ音源。溢れるアシッド感のAll Along The WatchtowerやSatisfactionのカバーが聴ける。
近年のライブも充実していて、懐かしいグループという感じは全くしない。常に自分たちの音楽のルーツ(思想を含めて)を大切にしながら、アップデートされてきている。
これは、2017年のライブで、Harvestere時代のナンバーを演奏している。
2018年のライブでのハードなサイケデリックナンバー。若い女性ドラマーの演奏がいい。こういう曲には重いドラムではなく、彼女のような知的でリズムが漂っていくようなリズムが必要で、それに応えるようなハードなギターソロも素晴らしい。
現在はグループ名を「Träden(木々)」と変えてアルバムをリリースしている。その音楽も幸福感にあふれている。

*****
1960年代の若者が理想としたコミュニズムは、ロシア革命から100年の歴史において、その理想とはかけ離れた自由への弾圧と独裁者を生み出すメカニズムに変容してしまい、民衆ではなくエリートによる支配を指向するものとなってしまった。彼らが思い描いた理想の社会は、その幻想の中から出ることはなかった。
でも彼らの音楽だけは、その理想を諦めることなく、今でも鳴り響き続けている。