
ロスレスストリーミングになったApple Music。いろいろと聴いて確かに音質が向上しているし、これまでのそこそこ音の良いBGMというか、気になるアルバムを試聴してチェックする用途から、音楽を真剣に聴く、鑑賞に耐えるものとなった。
もちろん全てが素晴らしいわけではなく、元の録音やデジタルマスタリングの状態、そこからストリーミングファイルが生成される過程でのイコライジングやエフェクト処理など、そのプロセスの影響も大きい。大雑把な印象では、古いものよりも2000年以降にレコーディングされた音源の方が品質の向上は著しいように感じる。元がデジタル録音されているものが有利なのかもしれない。僕はAppleMusicのみなので、AmazonHDや、TIDALといった他のハイレゾストリーミングサービスとの比較はできないが、送り出し型のシステム、再生側のアプリケーションが異なるのでまたニュアンスも変わってくるだろう。オーディオ専門のサイトでは「空間表現に優れたAmazonHD、高解像度のApple Music」という評もあるようだ。
USBケーブルをアコースティックリバイブにアップグレード
AppleMusicのロスレスでの再生音が想像よりも高品質なので、ほぼApple Muisc再生専用となっているiPadPro第二世代に接続しているUSBケーブルをアップグレード。これまではFURUTECH製の実売価格約9,000円のUSBケーブルを使用したが、これをアコースティックリバイブのUSBケーブル「R-AU1-PL」に変更(実売価格約17,000円)。

このケーブルは写真でもわかるように、データ信号線と電力線を完全に分離。2本に分かれていて、データへの電力線からのノイズ干渉を防止している。この効果は大きく、全体的にバックグラウンドが静かになり、音像へのフォーカスはシャープに、高域はナチュラルで中低域の厚みは増す。ぱっと聞いた感じは音数が減ったように感じるかもしれないが、それはノイズ干渉がなくなって本来の音になったからだと気が付く。いかにもデジタルっぽい、エッジーな表現ではないので、物足りないと思う人もいるかもしれない。あくまでもハイファイ指向。この価格帯では非常にすぐれたオーディオ用USBケーブルといえる。
では、実際にApple Musicでいろんなアルバムを聴いてみよう。
CD品質 44.1KHz/16bit or 48KHz/24bit
Agalloch / The White EP (Remastered) - 44.1KHz / 16bit

Agallochは、オレゴン州ポートランドのブラックメタルバンド。自然崇拝というか自然の美、冷たい冬の季節、メランコリーといったものが背景にある異色のグループ。このミニアルバムはトラッドミュージックかと思うほどアコースティックで、ほとんどがインストゥルメンタル。冒頭の子供の遊びの呪文のような声のフィールド録音からアコースティックギターが入るところは美しく、録音も優秀。
44.1KHz / 16bit は通常のCDと同じ品質。実際にCDとこのApple Musicのストリーミングを聴き比べると、音楽の実態感ではCDが有利だが、Apple Musicのストリーミングもほぼ遜色ない。CDでなくとも十分彼らの音楽の凛とした冷たい冬の大気が伝わってくる。
Apple Musicへ »
Sonny Sharrock / Guitar - 48KHz / 24bit

あれこれ聴いていくと48KHz / 24bit品質のものは多い。数値では44.1KHz / 16bit との差は僅かなように見えるが聴感上の差は大きい。44.1KHz / 16bit と比べると音楽の響きが滑らかで、音の立ち上がりや音の消え方がより自然になっている、
Sonny Sharrock(1940-1994)は米国のフリージャズギタリスト。スピリチュアルジャズとファンクとアバンギャルドが合体したユニークなスタイルで、初期はフルート奏者のハービー・マンのフュージョンサウンドで個性的なギターを聞かせ、晩年はビル・ラズウェルのグループでの演奏で若いオーディエンスに衝撃を与えた。本作は1986年のソロアルバムで、独特の太いディストーションのギターサウンドが心地良い。ロスレスになって音が痩せないので、ボリュームを上げて大きな音量で聴いてもうるさい感じがせず、演奏の熱度が一層際立つ。
Apple Musicへ »
Solid Space / Space Museum - 48KHz / 24bit

例えばシャッグスもそうだが、素人っぽい音楽への情熱がカルト作品を生み出すことがある。このSolid Spaceもそうしたグループのひとつ。10代のイギリスの二人が素朴なシンセとリズムボックスで、ポスト テクノポップを作り上げてカセットでリリースされる。その1982年の作品はカルトアイテムとなり、最近リマスタリングされてCDとレコードで再発された。
この種の音楽はリマスリングされると最初の混沌とした雰囲気がスポイルされてしまうことが少なくないが、このリリースはクリアになりながらもそうしたエネルギーを失っていない。ボーカルとチープなシンセサウンドの分離も明瞭で、その素朴な情熱が伝わってくる。
Apple Musicへ »
Wager / Parsifal - 44.1KHz / 16bit

カラヤン指揮・ベルリンフィルのワーグナーの「パルジファル」。1882年に初演されたワーグナーの最後のオペラ。晩年のカラヤンが時間をかけて取り組んだ演奏で、今聴いても色褪せていない。ストリーミングでの再生はCDやレコードを交換する手間が不要なので、オペラや長尺ものの交響曲に向いている。このカラヤンの演奏もロスレスになったことで十分鑑賞に耐える音質になった。
個人的にはこのオペラのハイライトはオペラ本編よりも15分及ぶ前奏曲にあるのではないかと思っている。沈黙から深く静かに始まる音は、後のアンビエント・ドローンミュージックの先駆者であることを示してはいないか。こういう耽美的な演奏はカラヤンにしかできない。
Apple Musicへ »
ハイレゾ音源 96KHz/24bit or 192KHz/24bit
今回のApple Musicのロスレス対応で初めてハイレゾ音源を真剣に聴くようになったが、確かにCD品質とは一線を画す高音質だと納得する。ハイレゾになるとより高域が伸びるように思うが、実際は低域の解像度の改善が著しい。良質のハイレゾ音源だと情報量が多く、アナログ再生に近いというか、よりナチュラルな再生音になり音楽の深みが増してくる。
Simon & Garfunkle / Bookends - 192KHz/24bit

サイモン&ガーファンクルの1968年リリースの4作目『Bookends』。全体で30分ほどと短いが、子供から老人までの人生を濃縮したコンセプトアルバム。音楽的にも実験的で充実している。「Save the Life of My Child」の冒頭の電子音や背景の悪夢の走馬灯のようなコーラスの扱いは、シュトックハウゼン的ですらある。このアルバムに大きな影響を受けた英国プログレバンドのYESは「America」をキュービズム的な大胆なアレンジでカバーする。
メジャーアーティストだけに古いマスターの管理状態もいいのだろう、192KHz/24bitとなってもデジタル固有のクセはなく、声やハーモニーの分離は一層明確で、バックのオーケストラやコーラスとも混濁することはない。優秀録音。
Apple Musicへ »
Royal Thunder / Wick - 192KHz/24bit

Royal Thunderは、ストーナーロックと呼ばれるジャンルの米国ハードロックバンド。ローリングストーン誌が「ジャニス・ジョプリンがフロントのレッドゼプリン」と評するほど、ボーカルとベースのMlny Parsonzには存在感がある。『Wick』は2017年リリースのサードアルバム。このアルバムは好きでロスレスになる前から何度もApple Musicで聴いているが、192KHz/24bitとなったことでアナログライクな厚みのあるサウンドとなった。こういうロックこそ、ハイレゾで聴きたい。うねるようなヘヴィなビートが際立ち、音楽のリアリティが増している。
Apple Musicへ »
Sunn O))) / Pyroclast - 192KHz/24bit

Sunn O)))は、シアトルで1998年に結成されたエクスペリメンタルメタルのグループ。ドラムなしのギター2本、ベース、ゲストでシンセとバイオリン、金管楽器などが加わる。大音量のアンプのフィードバック音のレイヤーがいくつにもの重なり、濃い音の霧がゆったりと形成されていく。ドローンメタルというジャンルで括られるが、ヨーロッパでは現代音楽として評価されている。メタルとしては抽象化されて過ぎているし、ノイズというには有機的過ぎる。
『Pyroclast』は2019年にリリースされた9作目のアルバム。大音量のフィードバックは、最初はアルバムカバーにもあるような濃い霧の塊のように聴こえるが、時間が経つにつれて、霧の中で目が慣れてくるように、その細部のアンサンブルがわかり色彩感すら感じるようになる。そいういう音響的な「体験」が彼等の音楽の魅力になっている。192KHz/24bitのハイレゾとなってより細部は明確となり、最後の曲では神秘的な抒情性まで表現され、ワーグナー的な世界観を感じさせる。
Apple Musicへ »
Anna Gourari / Elusive Affinity - 192KHz/24bit

ECMのハイレゾ音源となれば悪いはずはなく期待通りの音。ただApple MusicのECM音源全てがロスレス、ハイレゾ対応にはなっていないようだ。もう少し時間がかかるのかもしれない。
Anna Gourariはロシア出身のピアニスト。このアルバムでは、彼女と同郷のシュニトケ、ロディオン・シチェドリン、そして現在居住するドイツのウオルフガング・リームの現代音楽作品を中心にしながら、アルバムの最初と最後をバッハの小品でサンドイッチにする構成。『Elusive Affinity - とらえどこのない関係性』というタイトルになっているが、聴き手は彼女の知的であると同時に詩的に洗練された演奏から作品の関連性を思いを巡らすことになる。
192KHz/24bitのハイレゾならではの、ピアノの打鍵の強さ、余韻、ハーモニーのクリア表現。それにECM独特の残響が加わり、澄んだ水の底から音楽が湧き上がってくるようだ。コンサートでは得ることが不可能な、優れたレコーディングアートとしてのリスニング体験がある。
Apple Musicへ »
オーディオ的にどうなのか
これまでCDトランスポート+DACで聴いてきたものとApple Musicのロスレス/ハイレゾを比べると、音楽的な充実度や力感、サウンドステージの表現はCDが勝る。ただ、CDトランスポート+DACの再生は何年も追い込んでいるわけで、USBケーブルを変えただけのiPadProからの再生と同列に比較するのはフェアではないかも。逆に言えば「ただつないだだけ」で音質的も音楽的にも良質でポテンシャルが大きいことは確かだし、これからの調整でさらなる改善も期待できそう。
アナログ再生とは世界観が違うので単純な比較は困難。パッと聴いて情報量が多いのは192KHz/24bitハイレゾかもしれないが、その情報量が整理されていないような印象もある。表現が違うので僕の方が慣れていないのかもしれないが、ものによって192KHz/24bitハイレゾがアナログ再生に近いと感じることも多かった。
*****
これまで僕の中でBGM的な扱いだったApple Musicが、音楽を聴く、鑑賞にに耐えるものになった。でもこれで、レコードやCDの購入量が減るかというとそうはならないかも。Apple Musicで聴いてよかったものはやはり欲しくなるんだろうな....。
shigeohonda.hatenablog.com
































![Live At Knebworth 1990 (Vinyl) [Analog] Live At Knebworth 1990 (Vinyl) [Analog]](https://m.media-amazon.com/images/I/51bhbRP6GyS._SL500_.jpg)





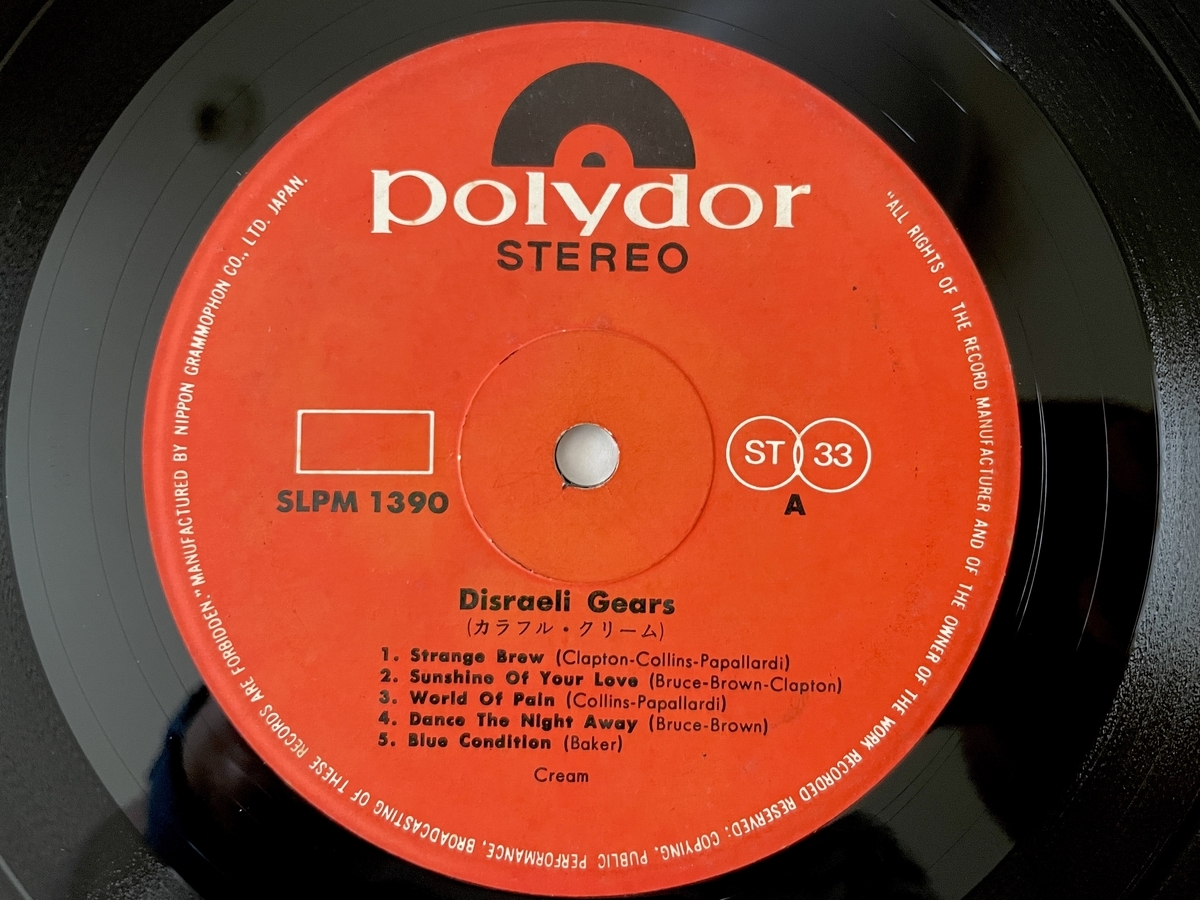













![Live at Tubby's [Analog] Live at Tubby's [Analog]](https://m.media-amazon.com/images/I/51IFolrTvBL.jpg)





